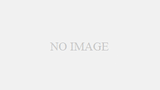B型事業所では、送迎サービスを提供しております。
自宅から事業所まで送迎があると、ご家族も安心して送り出せますよね。
制限をつける理由
以前は、片道30分かかるパートナーさん(当社での利用者さんの通称)の送迎をしておりました。距離にすると20km近くあります。パートナーさん自身での運転をする場合、既往症のテンカンなどが発生することでの事故リスクがあります。そのため、送迎サービスを利用することが、ご自身・家族の安心・事業所の安心にもつながります。
しかしながら、問題を抱えることもあります。人員に余裕があり、送迎専門のスタッフを雇っていれば問題ありませんが、職業指導員であるスタッフが兼務する場合です。
朝と夕方往復で1時間ずつ送迎に出ると、前日・その日にあったことの情報共有ができなくなります。
例えば、〇〇さんが作業中に□□さんと些細な言い合いをしてしまった場合に、翌日の作業配置を考え直す必要が出てきます。その原因や状況がわからないスタッフは翌日の対応をいつもと同じようにしてしまうのです。
特に1日外作業に同行したスタッフが、送迎までしてくれるのは大変ありがたいのですが、
ますます情報共有ができなくなる悪循環になり、事業所に悪影響がでます。
なぜ、制限をつけた方が良いかに気づけたか
経理担当者が違和感に気づいたのは、ガソリン代が増えたためです。最初は原油高が原因程度に思っていたのですが、日向事業所ではそんなに影響がなかったのです。なぜ延岡事業所だけあがる?というちょっとした違和感から、原因をたどると遠方への送迎がきっかけでした。
そしてそれは、表面的な問題であることにも気づけました。
送迎時間が長いと、スタッフ間の会話が減るため、仕事に支障ができ、スタッフ間に変な空気が流れます。そうすると、パートナーさんたちは敏感なので、すぐに気づき、体調不良者や欠席者が徐々に増えてきます。
パートナーさんたちの利用が減れば、お支払いする工賃も減ったり皆勤手当も減ったりするのです。
ほんの些細なことかもしれませんが、その影響は全体に与えるものです。
会計帳簿や数字に現れることは、何かのサインですね。
既に圏外の方への対応はどうする?
現時点では、現状維持が良いと思っています。
当初は送迎をするとのことで利用決定したため、大きな変更があれば動揺を与え、精神的な負担につながります。
そのため、4月や12月など、年度替わりや年末年始くぎり、また、更新月など相談員さんを交えて、今後のサポートについて話すのが良いかと思います。
就職したら、自分で通勤することは必須になります。B型事業所は、障がい者の職業訓練所という意味を考えれば、早めの段階から自分で通勤する工夫や回りのサポートがあっても早すぎることはありません。
もちろん、就職をせず、B型事業所にお仕事をしに来る方もいらっしゃるので、今まで通り送迎をすることには何ら問題はありません。
まとめ
大事なことは、「今までと通り」という固定概念を外すことです。
この人は通勤できない、など決めつけずに、今後どのように訓練していきたいのか、
普段の会話や声掛けから、パートナーさんの意思を聞いていきましょう。
この2ヶ月間で、就職したいパートナーさん2名が自家用車で毎日通勤することになりました。
今まで通り、という垣根を取っ払って、一人ひとりにあったサポートを常に見直すサイクルが大事です。その結果、スタッフによる送迎の負担も減ることで、よりスタッフがパートナーさんと会話する時間が増えたり、スタッフ間での情報共有の時間が増えたりし、事業所も好循環に入ります。
今日、パートナーさんと将来の方向性について1分でも話してみませんか?
■長男&長女日記(2歳6ヶ月&0歳8ヶ月)
長男は、お腹を壊すのではないかくらいよく食べます。保育園から帰宅して、バナナ1本・スティックパン2本、晩ごはんに納豆とご飯、おかずをたいらげます。
長女は、歯磨きをしました。下の歯が2本生えているので、歯磨きシートをつかいました。かなり嫌がるのはお兄ちゃんと一緒です。
■1日1%の成長
・ZOOMの利用制限を超えたら入り直して、無料で2回使う(頻度が増えれば有料プランにします)
・天領うどんで、うどんを食べず好きなおでんを食べる
・切り干し大根30箱を搬入する